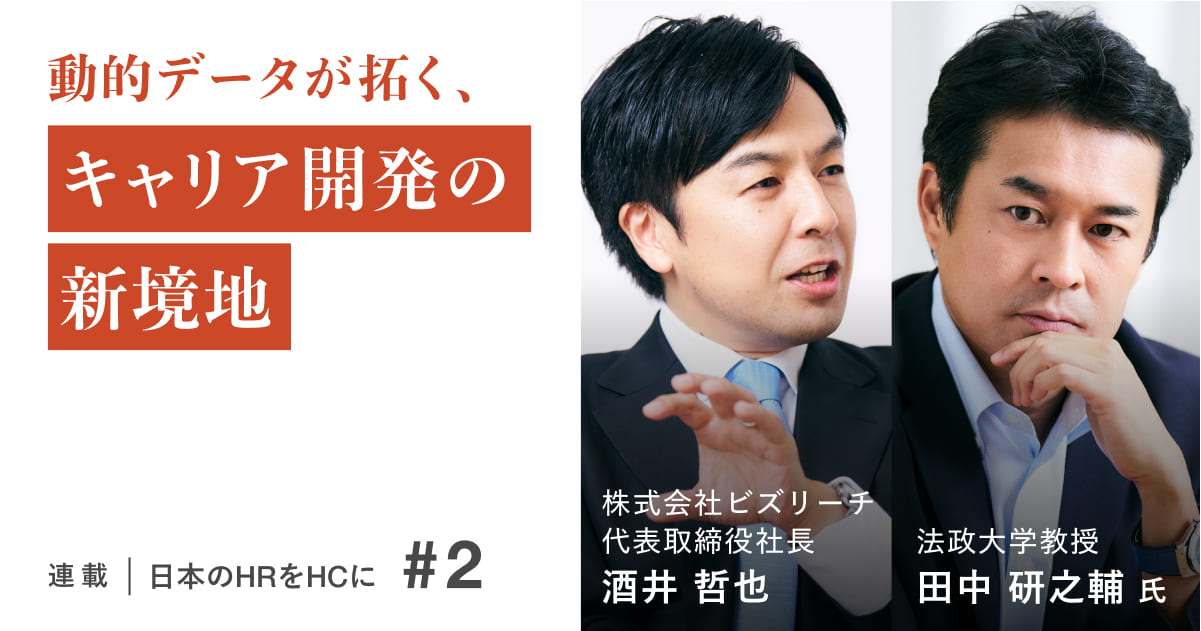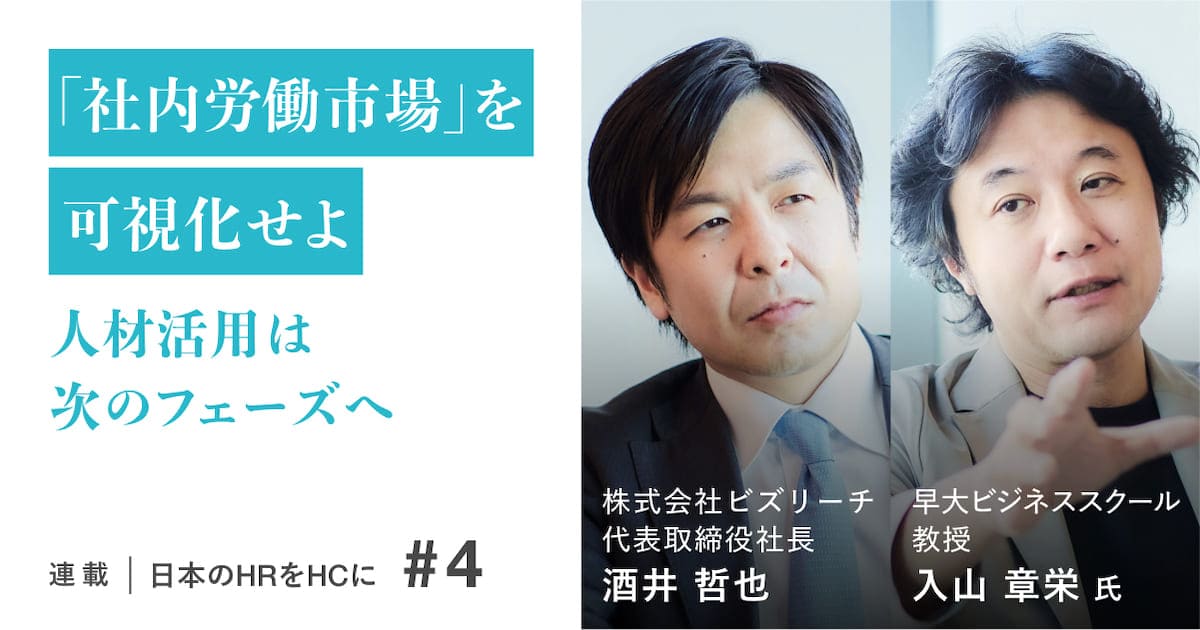連載 日本のHRをHCに
眠った人的資本を稼働せよ
カギ握る「やる気の創出」と「マッチング」
慶應義塾大学教授 鶴 光太郎氏
×
株式会社ビズリーチ代表取締役社長 酒井 哲也
「スキルの拡大だけでなく、スキルをもっと稼働させることに目を向けるべきだ」。内閣府で長く雇用規制改革の議論に携わった鶴光太郎教授(慶應義塾大学)は、そう話します。社会に定着するにはまだハードルもある「人的資本経営」を実現するため、経営者に、人事に求められるものとは何か。当社社長の酒井哲也が伺いました。
「同じスキルの人材が、さらに活躍する方法」を考える
酒井
近著の「日本の会社のための人事の経済学」で、日本の企業は人的資本経営を考えるとき、従業員の「スキルの拡大」に気を取られすぎていて、「スキルの稼働」に目を向けられていないのではと指摘されています。
鶴
過去、資本といえばお金のことでした。元手としてのお金を何かに投資して事業をし、どれくらいのリターンを得るかというのが事業における資本の基本的な考え方です。
これを人に置き換えたとき、例えばリスキリングや人事異動などで「新しいスキルを身につけてもらう」というのは、元手となるスキルを拡大させているととらえられます。
しかしより多くのリターンを得る方法は、「元手を増やす」だけではありません。元手の額は同じでも、稼働水準を高めてより効率的に成果を出してもらう方法があります。「ウェルビーイング」という言葉も注目されるようになりましたが、企業経営における意味を簡単に言えば、従業員によりやる気をもって働いてもらうようにするということです。そうすれば、同じスキルセットでもより多くのリターンが得られるという考え方です。

- プロフィール
- 鶴 光太郎(つる こうたろう):慶應義塾大学大学院商学研究科教授。経済産業研究所(RIETI)プログラムディレクター/ファカルティフェロー。2012 年より現職。OECD(経済協力開発機構)のエコノミストや日本銀行、経済産業研究所などの研究員を歴任。2013~16 年、内閣府規制改革会議委員(雇用ワーキング・グループ座長)を務める。近著に「日本の会社のための人事の経済学」(2023、日本経済新聞出版)。
酒井
過去、日本では「就職」というよりも「就社」といった感じで、最初に入った会社にずっと勤めるのがいいという価値観が強い時代がありました。それに伴う労働慣行が従業員のウェルビーイングを阻害しているのでしょうか。
鶴
職務ではなく会社にエントリーする「メンバーシップ型雇用」と、特定の職務に従事することを前提にした「ジョブ型雇用」には、一長一短があります。どちらのほうが優れているというものではありません。
私はジョブ型を推進してきた立場ですが、それは時代の変化に鑑みたときに、旧来のメンバーシップ型ではひずみが大きくなると考えられるからです。かといって、しばしば指摘されるように欧米の伝統的なジョブ型を日本に入れてもうまくいかないというのは、その通りです。
人口減で、黙っていれば国内市場は縮小します。さらに感染症の流行や災害、技術革新など想定外のことがいくつもあり、かつての大企業が買収されるといったことが起きています。一つの企業に、30年40年にわたって安定的な成長を期待することが、なかなか難しい時代です。
そうなると、「定期的な人事異動による育成」や「年功型の昇格・昇給といった後払い要素のある人事・賃金制度」など、長期雇用を前提とした仕組みは成立しにくくなります。それに代わる形で、いかに従業員のウェルビーイングを実現するかが企業には問われているのではないでしょうか。
「アウトサイドオプション(外部の可能性)」が大事
酒井
経営する側の立場として難しいのは、従業員が望むものって、それぞれ違いますよね。めちゃくちゃ働いて高い給料が欲しい人もいれば、家庭の事情などに合わせて、柔軟に働きたいという人もいる。
従業員の声を丁寧に聞くのは大前提なんですが、全員の事情に完璧に合わせることはできません。そうすると「うちの会社としては、こういう考えで、この価値観を大事にして、だからこういう仕組みにしている」っていうことをはっきり打ち出すことがとても大事だと感じています。
鶴
おっしゃる通りです。いわゆる企業の「パーパス」ですよね。人的資本経営においても、それがとても重要です。
長期雇用を前提にできれば、従業員はある程度同質化します。しかしそうでない、多様化した組織の中では結集軸がより必要になります。
優秀な人ほどそれを重視している印象がありますね。すでに十分なスキルと評価があって、それをどう会社や社会に還元するかということを考えている人ほど、何を大事にしている会社か、そしてそれをどう制度などに落とし込んでいるかを見ている気がします。
「会社が方針を決める」というと、全体主義のようにとらえる方もいるのですが、これはそうではありません。むしろ会社のパーパスに対して、「自分はどうするか」ということを個人が考えることになります。個人も「マイパーパス」のようなものを持ち、会社の方向性が自分のパーパスに合わないと思えば、会社を去る。そうしたことがもっと起きてくるのではないでしょうか。

- プロフィール
- 酒井 哲也(さかい てつや):2003年、慶應義塾大学商学部卒業後、日本スポーツビジョンに入社。その後、リクルートキャリアで営業、事業開発を経て、中途採用領域の営業部門長などを務める。2015年11月、ビズリーチに入社し、ビズリーチ事業本部長、リクルーティングプラットフォーム統括本部長、取締役副社長などを歴任。2022年7月、ビズリーチ代表取締役社長に就任。2022年10月、ビジョナル取締役を兼任。
酒井
私たちが会社として目指していることは、「選択肢と可能性の可視化」だと思っています。今の会社が「合わないな」と思っても、外部に「もっと合う会社がある」と思えなければ、人は外に踏み出すことはできません。
選択肢があれば、より多くの方が自分に合った職場で活躍し、社会全体で働き手のウェルビーイングが改善します。それが人的資本経営、社会の生産性の向上につながっていくと考えているので、私たちは事業を通じて、それに貢献したいですね。
鶴
アウトサイドオプションを自覚できているというのは、本当に大事です。必ずしも実際に転職する必要はありませんが、外部に異なる可能性があると思うだけで、会社に対して個人が要求できるようになりますよね。それが「声」となり経営に取り入れられていくという流れが、人的資本経営には不可欠なのだと思います。
以前に比べれば、企業と従業員の間に緊張関係は出てきたと思います。望ましい評価や環境がなければ出ていくよ、と個人がなってきていますよね。
ただ、このときにこそ大事になるのがジョブ型の人事雇用制度です。個人が自立・自律的にキャリアを形成しようとなったときに必要になるのが、「どの会社のどのポジションならば、どんな環境でどんな業務に従事できるのか」という情報です。
個人が望ましい働き方を選択するのと、ジョブ型の普及は表裏一体です。ビズリーチさんのようなオンラインジョブサーチが広がっているので、徐々に環境は整ってきているといえますが、まだまだ十分とはいえません。
「リスキリング」もキーワードになっていますが、そのスキルを身につけたら、年収やポジションがどうなるか分からなければ、人は動きません。逆に、それさえ分かれば「個のスキルを身につければ年収がこう変わるからやってみよう」となる可能性があります。
社内外で人材をマッチング
酒井
外部の可能性についてお話しさせていただきましたが、特に大企業などでは同じことが社内でもいえると思っています。実は「社内版ビズリーチ」といって、社内でもポジションやスキルを可視化して、必要な人材をマッチングしていく機能を提供しています。
おっしゃっていただいたように、個人にとっては必ずしも転職することだけが答えではありません。また企業としても、社内にある可能性を知ってもらえないまま、優秀な人材が外に出ていってしまうのは望ましくないでしょう。
異動の調整は人事部門が一手に引き受けているという企業も少なくないと思います。しかしこれは、適切なマッチングをしようとすればするほど、極めて複雑な作業になります。「職務内容の定義」や「個人の職歴やスキル、人柄」などのデータを適切に保持することが求められます。
私たちもやっていて分かりますが、これを自分たちでできる人事部門というのはなかなかないだろうと思います。当社はそれを、AI(人工知能)の技術も使って支援できるのではと考えています。
鶴
なるほど。AIにできることは加速度的に広がっていますが、定性情報の多い人事領域で活用できれば、伸びしろは大きいように思います。
IT系の企業や、多大なシステム投資をして社内にもDX人材を豊富に抱える一部の大手製造業など、自前で対応できる会社もあるかもしれませんが、多くの企業は難しいでしょう。
そうすると、それを支援するビズリーチさんの存在は大きいのではないでしょうか。
そもそも「そうした仕組みが必要である」ということを、経営陣が理解していなければ、個人の人脈や印象に頼った形での配置をするしかないように思います。ここも一つの大きな壁で、JD(Job Description:職務記述書)を作ったからといって、それで終わってしまってはあまり意味がないんですよね。
欧米はJDが雇用契約に記載されます。それに沿ってスキル把握やマッチングが行われなければ、せっかくのJDも無用の長物ですから、ジョブ型の神髄は業務を定義したうえでの配置・マッチングにあるといえます。

経営者が理解しておくべきこと
酒井
人的資本経営に先端的に取り組んでいる企業というのは、やはり経営陣の理解やコミットの度合いが大きいのでしょうか。
鶴
それはそう思いますね。人事分野に限らず先端的な挑戦をしている企業ほど、トップと人事責任者の距離がすごく近い印象はあります。その連携が自然なんですよ。これは製造業でも非製造業でも一緒です。
事業計画に対して、人事は「じゃあそれを実現するのに適した体制を作ろう」となるわけですが、体制づくりがうまくいかなければ事業計画にも影響します。お金や、原材料などのモノと同様、人も計画通りに配置できなければ事業に影響します。しかし、カネやモノほど、人のことは意識されていない会社は少なくない気はします。
酒井
採用や後任探しで「どんな人に来てほしいか」と聞くと、多くの場合「あれもこれもできる人」となりがちです。たとえていうと(米メジャーリーグの)大谷翔平選手のような。でもそんな人は仮にいたとしても、超人気ですから、最低でも多額の資金が必要になります。
採用の妙は「大谷選手は獲得できない」となってから、どうするかにあると思うんです。自分のチームに必要なのはバッターなのかピッチャーなのか。ホームランを打つ人なのか打線をつなげる人なのか。そう考えればチームごとに違いがあって、あるチームでは評価されていない選手が別のチームでは必要とされることがあります。
鶴
スポーツもそうですし、海外の雇用制度というのはそれに近いところがあるかもしれません。
私はOECDで働いたことがありますが、国際機関などの中で、自動的に給与が上がっていくなんてことはありません。給与を上げたいなら、自ら手を挙げてより高いポジションを得にいくか、そうでなければ出ていくか。個人も「自分のことをより評価してくれる場所」を常に探します。それが世界では常識で、逆に言えば、労働市場に流動性が少なかった日本は、そうしたチャレンジが阻害されてきたと考えられるかもしれません。

酒井
鶴先生は大学で若い世代とも日常的に接点があると思いますが、これからの時代、企業が個人に選んでもらうために重要なこととは何だと思われますか。
鶴
そうですね。傾向として感じるのは、「成長」を強く意識しているということでしょうか。一時、ブラック企業・ホワイト企業といった言い方が話題になりましたが、「ホワイトすぎて辞める若手」が報道されていますよね。あれは一つ象徴的なことだと思います。
若い人も浅はかに「厳しいのは嫌、緩ければいい」などとわがままを言っているのではないのだと思います。やり方の合う、合わないはあると思いますが、言葉を換えると「自分に成長の機会を与えてくれるか」を見ているのだといえるのではないでしょうか。より成長意欲が強い人は、性別に関係なく、いわゆる労働環境がきついといわれる会社にも自ら入っていきますしね。
あとは、従業員が自分のスキル開発を「選べる」仕組みでしょうか。いま日本で議論されているのは、あくまで企業が「このスキルを持っている人にいてほしい」というのがあって、そこに向けて人を育成するような仕組みです。これに対して、企業側の思いと別に、従業員が身につけたいスキルや経験を選んでいけるような仕組みがあるといいと思いますね。
欧米ではそうした発想のメニューが取り入れられ始めています。日本では難しいかもしれませんが、でも働く人の視点では、そちらのほうがいいのは自明ですよね。
酒井
企業からすると「自分のところで育成コストを払って他社に行かれたら嫌だな」という思いが壁になりそうですね。
鶴
気持ちは分かりますが、でも「育てる意識」がない会社からはどちらにしても人が離れていくのではないでしょうか。だとすれば、離職する可能性は受け入れるしかないようにも考えられます。
一つの育成施策で効果をみようとすると、「そのメニューで開発したスキルが社内でどう使われるか」ということに目がいきがちですが、総体としてみれば「メニューがそろっているから優秀な人が集まる」ということも考えられます。
リクルートさんのように、人材輩出企業になって、大きな成長を遂げた例もありますからね。それはご出身の酒井社長もよくご存じなのではないですか(笑)。
酒井
当社は「変わり続けるために、学び続ける」という価値観を大事にしています。企業も個人も、最初から正解を出そうとするのではなく「合わなかったら変えていく」といった姿勢を持つことが、人的資本経営においても重要なのかもしれませんね。
本日はありがとうございました。