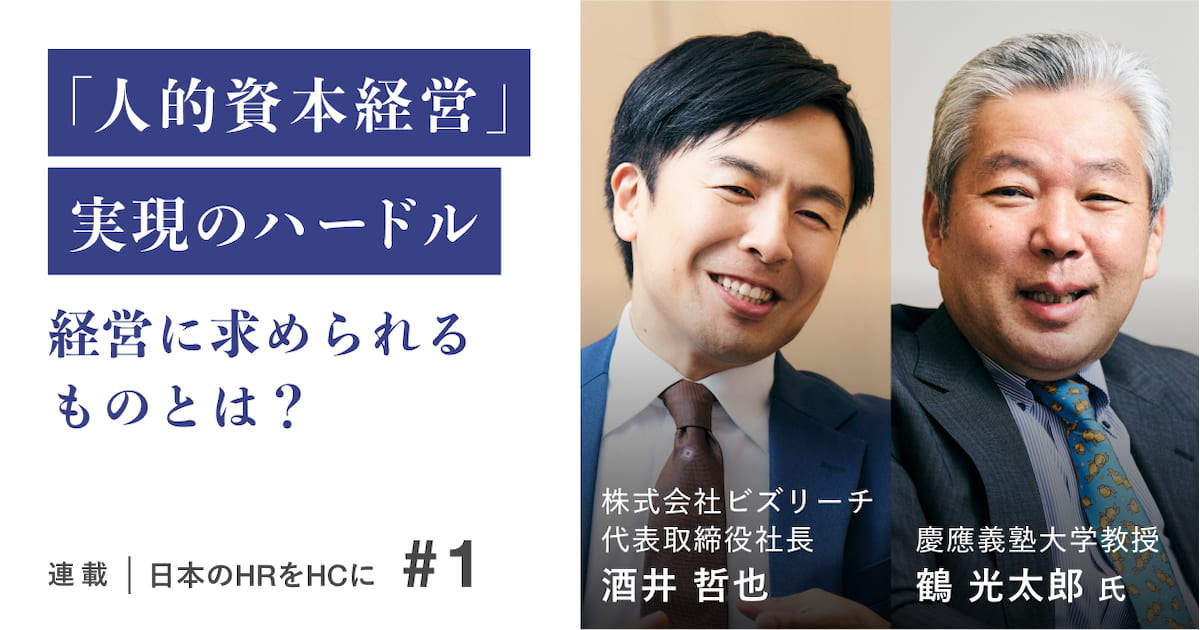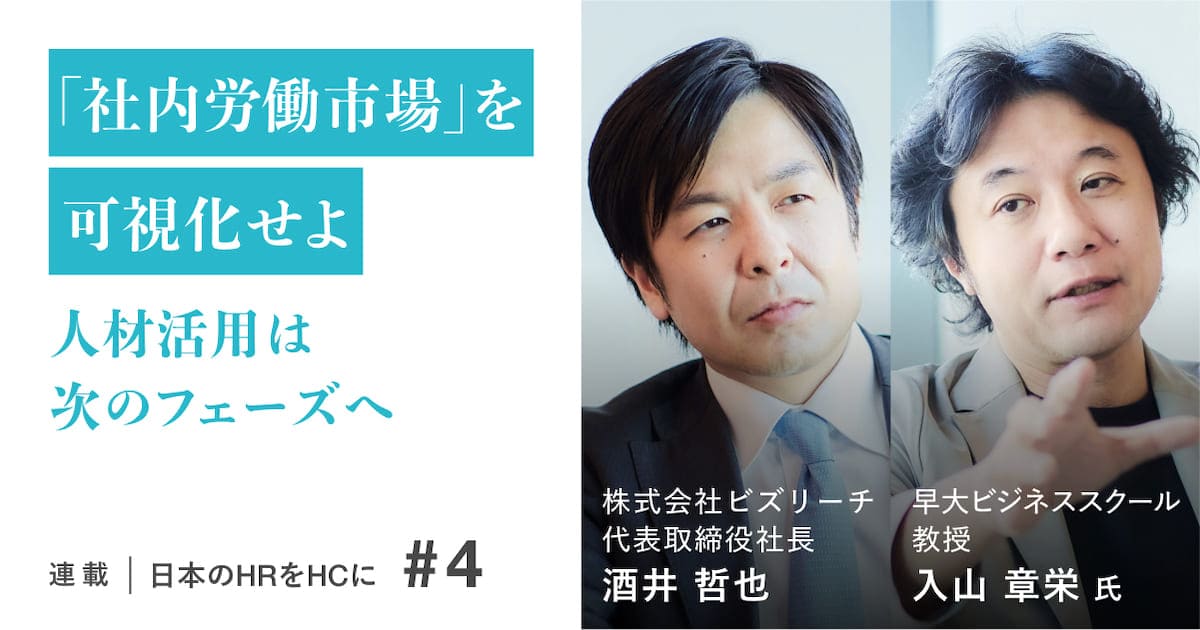連載 日本のHRをHCに
「キャリア開発の現場にデータを」
高度化した人事業務の処方箋
法政大学教授 田中 研之輔 氏
×
株式会社ビズリーチ代表取締役社長 酒井 哲也
個人が主体的に自らのキャリアを選んでいく「プロティアン・キャリア」を日本で提唱する法政大学の田中研之輔教授。個人に向けた発信を多くされていますが、人事領域における企業支援も非常に積極的にされています。人的資本経営を根付かせるうえでの最大の壁とは。当社社長の酒井哲也が伺いました。
やるべきは「人のポテンシャルを最大限発揮すること」
酒井
これまでに37社の企業顧問と、大企業が49社参加している「はたらく未来とキャリアオーナーシップコンソーシアム」の戦略顧問をされていると聞いています。そうしたご経験から、人的資本経営を実現する際の最も大きな壁は何だとお感じですか。
田中
人的資本経営と言うと難しく聞こえますが、考えるべきは社員一人一人のポテンシャルを最大限発揮すること。これにつきます。もしポテンシャルを発揮するのにブレーキになっていることがあれば、キャリア開発の手法で伴走しながら、ブレーキ要因を取り除く。これが基本的な考え方です。
そのうえでご質問にお答えすると、現在、向き合うべき課題は、「この国で働くビジネスパーソンのキャリアオーナーシップのなさ」にあります。個人がキャリアは自分のものであると自覚し、自ら主体的にデザインしていく姿勢の欠如が、大きな問題だろうと思います。
ただし、これは個人の意識に問題があると言っているのではありません。欧米では幼いころから「あなたはどうしたいの?」と日常的に聞かれますが、日本ではそうとは言えません。これはどちらがいいというものではありませんが、相対的に日本は個人の意思よりも所属コミュニティーの論理やコミュニティ内での立場を重視しがちです。組織にキャリアを預けるという状態が続いているとも言えます。
ところが、人的資本経営を定着させるためには、個々人がそれぞれのキャリアにオーナーシップをもって、「やりたいこと」を追求する姿勢が不可欠です。オーナーシップが希薄だとすれば、みながそれをもってやりたいことを追求できるように、企業や社会が変わっていかねばなりません。

- プロフィール
- 田中 研之輔(たなか けんのすけ):法政大学キャリアデザイン学部・大学院教授。専門はキャリア開発。一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事。UC.Berkeley元客員研究員。「プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本術」など著書多数。
酒井
個人のやりたいことをサポートすると、逆に企業競争力を阻害するのではないかという考えは根強いようにも思います。
田中
分かります。しかし個人にやりたいことを我慢させて、会社の都合になかば強制的にあわせさせることが、個々の成長のブレーキ要因なんです。
役職定年前後のベテラン社員の停滞が課題とされますが、みんな趣味に興じているときは夢中で元気ですよ。趣味のゴルフなら自ら動画とかを見て研究したり分析したりするのに、会社からの「やらされ仕事」ではそうしない。なぜかと言えば、仕事やキャリアが「会社のためのもの」となってしまい、「自分のもの」という感覚ではないからです。
酒井
人は自分が意思をもって決めたことなら、納得感や責任感をもって取り組むものだと思います。結果が仮に望ましくないものだとしても、自分が決めたことなら「仕方ない」と思えます。そうした感覚があれば、めんどくさかったり、他人がやりたがらなかったりすることにも没頭できるということでしょうか。
田中
今の学生などは、主体的にキャリアを形成していくという意識をもっています。しかし大企業などに入ると、大半の人は組織にいったんキャリアを預けてしまいます。「新人なんだから、まずは吸収することに集中する」といったことが新入社員研修でたたき込まれてしまうわけです。新入社員研修も、キャリア自律意識を育てていくプログラムに変えていく必要があります。
会社の「管理職」という言葉もよくないですよね。「規範を守らせ、業務をコントロールすることが仕事」のようなイメージです。強すぎる上下関係を想起させる「上長」とか「部下」とか、そういう言葉も本当は使いたくありません。特に、「部下」という言葉は、私のライフミッションとして、企業からなくしていこうと考え行動しています。
高度・複雑化した人事の業務
酒井
研修などを設計しているのは人事部です。「管理する」組織ではなくするために、具体的にはどんなことを人事や経営はすべきでしょうか。
田中
数十社の企業現場を見て思うのは、企業で行われている研修などの多くは前年の踏襲です。例えば、「8時間×2日間の管理職研修の目的と明確なゴールは何ですか?」と聞いても、明確な回答が得られないことが少なくありません。
管理職はそれぞれが「終わりなき仕事」に忙殺されています。そんな人材の時間を奪う長時間研修は、より効率的なプログラムに変更し、オンライン学習でセルフ・リスキリングを促進させるなどして負担を最小化すべきです。何のためにやっているのか、目的は果たせているのか、より効果的なやり方はないのか。そのあたりを徹底的に科学しなくてはいけません。
そのために、CHRO(最高人事責任者)などの人事トップは、社長やCFO(最高財務責任者)、経営企画などと人事戦略について合意をとらないといけません。中期経営計画など、向こう3年ほどを見据えた人材開発の計画を練る必要があります。あらゆる研修や採用を、その戦略に基づいて企画実行するのです。
有名な話ですが、韓国のサムスン電子は毎年、製品の研究開発費と同じくらいの規模で人材への投資をしています。「基本ルールを教える」といった研修とは、温度感が違うのは明らかでしょう。
酒井
私もお客様と話していて、人事の仕事ってこの数年間で本当に複雑化、高度化しているように思います。採用だけでもそうなのに、ご指摘の人事戦略の策定、各施策の定量的な効果把握など、メンバーに求められるスキルの幅もものすごく広がっています。
「とてもではないが、自分たちだけでは対応しきれない」という企業様は多いです。だからこそわれわれは、採用だけでなく人事の方々が感じる課題の解決を支援できる存在にならなくてはいけないと思っています。
例えばAI技術を使って、社内の配置を最適化したりとか、個々のスキル開発の指針を示したりだとか。その効果を可視化して経営にレポートするなど、そういうふうに頼っていただける存在を目指しています。大きなことを言うようですが「日本の人事になる」というイメージです。

- プロフィール
- 酒井 哲也(さかい てつや):2003年、慶應義塾大学商学部卒業後、日本スポーツビジョンに入社。その後、リクルートキャリアで営業、事業開発を経て、中途採用領域の営業部門長などを務める。2015年11月、ビズリーチに入社し、ビズリーチ事業本部長、リクルーティングプラットフォーム統括本部長、取締役副社長などを歴任。2022年7月、ビズリーチ代表取締役社長に就任。2022年10月、ビジョナル取締役を兼任。
田中
企業からすると、外部に戦略人事部を組成するということですね。なるほど。ニーズは確実にあるし、ビズリーチさんのような会社は、そうした変化を絶対に起こさなくてはいけないと思います。過去に人事メンバーに求められたスキルや経験だけでは、対応できない課題が増えているのは確かだと思います。
私が仕事でご一緒させていただいている人事の方は誰もが、社員のために、より良いキャリア開発プログラムを構築しようと日頃から努力されています。しかし、目の前の業務もあるので、なかなか戦略的に実行できないもどかしさを抱えています。
おそらく、人的資本経営の実現の中心的役割を担う人事部や人材開発部には、戦略を練れる人的資本経営の戦略コンサルタントのようなプロフェッショナル人材も必要ですし、目的に沿って魅力的な研修をデザインできるクリエーティブディレクターといった方も必要でしょう。もちろん、デジタルツールの活用も不可欠です。リソースも限られているなか、これらを全部自前でやろうとする必要はないと思います。
動的なデータの分析と活用を
酒井
田中先生から見て、人事領域を専門とする会社に期待したい役割はありますか。
田中
3年くらいで取り組んでほしいことがあります。それがキャリアの動的ポートフォリオの分析です。
人事領域ではいま、いろんな診断ツールが増えてきています。私も企業さんと組んでさまざまなキャリアに関する指標設計をしており、「取れるデータ」は増えています。でもその運用面で言うと、ほとんどが「ある一時点」の静的なデータ(Static Data)の活用にとどまっています。「今あなたはこうだから」「今の組織の状態はこうだから」といったような。
一企業のなかだと、それを経年変化で追っていくことしかできません。しかしさまざまな企業のデータを集められる外部企業ならば、A社、B社、C社それぞれでどんな経験を積んだ人材が、どう躍動していったのかを見ていくことができます。
人材開発領域で価値をもつのが、社員の動的データ(Dynamic Data)です。
私が「キャリア資本」と呼んでいるものも、個々人の動的データの一つです。個人のスキルや経験、人脈は所属企業の枠を超えて積み重なり、資本化されていくのです。一時点の選択のよしあしだけを見ようとするのではなく、長い目で見てキャリア資本が蓄積された経路を分析する。これが、専門企業にしかできないことだと思いますね。

酒井
私はスポーツが好きで、メジャーリーグのセイバーメトリクスの進化を個人的に追っています。野球に統計の手法を導入して、選手の価値評価を劇的に変えたと言われるものです。
現役選手の価値評価に目がいきがちですが、実はこの手法がいま、選手の発掘や育成にも用いられているんです。例えば、過去に所属したどんな選手がその球団で伸びたのか、どんなプレーの精度が上がったのか。そうしたデータをもとに、どの選手がチームに来てもらいやすいか、どう育成したら伸びる可能性が高いのかを考えているんです。
ものすごく大ざっぱに言うと、「どんな小学生にどんな環境を適用すると、次の大谷翔平選手になる可能性が高いのか」を把握しようとしているんです。一つ一つのプレーを評価しやすい野球という競技の特性もあるとは思いますが、基本的な考え方はとても興味深いと思っています。
田中
私も、いま最も読んでいる英語の論文が、医療とスポーツの分野の統計分析です。理由は明確で、この2分野は動的データの分析がしやすいんですよね。スポーツには勝ち負けや得失点、医療には生死と治った・治らないがある。
キャリア分野に関する複雑な要因連関は丁寧に読み解いていく必要がありますが、スポーツや医療の分野の研究実績は非常に示唆的です。また、日本でキャリアの話ってこれまで「心理学的アプローチ」偏重だったんですよ。だから「個人のキャリアの悩みをいかに解消するか」が主眼です。
でもキャリア開発に関連する欧米系の学術論文なんかを見ると、アプローチの方法は2つあると明確に書かれています。一つが心理学で、もう一つが私の専門である社会学だと。社会動向を統計手法で解き明かしていくのが社会学の本領ですから、酒井さんのおっしゃることは、まさにこのもう一方の社会学アプローチです。私も、これがもっともっと進んでいかなければいけないと思っています。
酒井
医療のお話も出ましたが、当社でもキャリアのデータは個人ができるだけ定期的に更新・確認するほうがいいと呼びかけています。「キャリアの健康診断」と呼んでいますが、そうした基礎データがあるからこそ、個人も健康増進のための方策がとれるわけですよね。
田中
はい。数値は中立ですから、それがあればより、個人が人事評価などで上司や会社と交渉することが可能になります。今は多くの企業で、本来は把握しなければいけない数値やデータを見にいこうともしないで、感覚でさまざまな人事評価や異動といったことがされてしまっています。これを変えられると、個人がキャリアオーナーシップを持つことにもつながると思います。
「人事からもっと社長を」
酒井
メリットやデメリットが明確なほうが人は動きやすいですよね。リスキリングにしても「そのスキルを身につけたらどうなるのか」「年収はどれくらい上がるのか」、そういったことが分からないと重い腰は上がりません。
欧米は、大学で学んだ専攻が職業に直結しますよね。そうした感覚で「これを身につけたからこうなる」ということをもっと分かりやすくすれば、多くの人がより積極的にスキル開発に取り組むと思いますし、ひいては社会の生産性向上につながるはずです。

田中
個人と企業組織は、本来両輪です。どちらか一方の都合だけ押し付けようとしても、うまくいきません。しかし今はそれが分断されています。
個人の「どうキャリアを作るか」という書籍と、企業の「人的資本経営」の書籍は、いまは本棚が分かれていますよね。でも実はこれは、表裏一体です。人事部門でそれに気づいている方は大勢いると思いますが、経営層や一般社員の理解はまだまだ進んでいません。それをどうにかしていかないといけません。
いわゆる「ワーク・ライフ・バランス」や、女性活躍などの「ダイバーシティー」を意識するところまでは、社会が到達した気がします。しかし個人のキャリアを企業や社会が本気で開発していこうというところまでは、まだまだ至っていません。
酒井
人口が減るなかでは、生産性を高めることは避けては通れないですよね。
田中
はい。社員の一人一人の可能性に向き合うキャリア開発を各組織で展開していけば、伸びしろは十分あります。コロナ禍は取り組みのギアを一つ上げたと思いますし。
また、先日英国が週休3日の法制化に動くというニュースが出ていましたが、世界的にはこの流れは止まらないと思います。テクノロジーの進化を効果的に活用しながら、働き方の生産性を高めていく「これからの組織文化」を作っていったほうがいいでしょう。
制度設計や職種にもよる部分はありますが、そうなれば今よりももっと少ない人手と労働時間でいかに成果を出すかということが問われます。人事の重要性はさらに増すのではないでしょうか。
酒井
人事部門はより多くの企業のなかで「憧れの部署」となり、優秀で多彩な人材が集まるようになっていくのかもしれません。
田中
そうしていきたいですね。実は個人的なライフミッションとして、日本の大企業でCHROから社長になる事例を出していきたいと思っています。どうしても営業とか技術開発、あるいは経営企画部門の出身者がトップに就くことは多いのですが、人事からそういう人が出て初めて、人的資本経営が定着していく気がします。
ビズリーチさんにはぜひ、「ああやっぱり人事を経由したからこの人のキャリアは花開いたんだな」というデータが分かるようにしてもらえると(笑)。
酒井
当社としても、便利な転職・採用ツールを提供していればいいとは思っていません。もちろん、その機能も磨き続けていくのですが、これからは困り事を解決するためのパートナーとしての存在感を高めていくつもりです。
企業としても、社員としても今までよりも難しい挑戦となります。ですがそれは社員にとっても「機会」となり、働く場として選んでもらえることにつながると信じています。
田中
私たちは、一人一人の可能性を伸ばしあうために組織で切磋琢磨しているのです。そして、組織はより良い社会や未来を創造していくために、ビジネスインパクトを生み出しているのです。何歳になっても仕事にも趣味にも没頭する、人生で躍動するビジネスパーソンを一緒にプロデュースしていければと思います。
酒井
本日はありがとうございました。