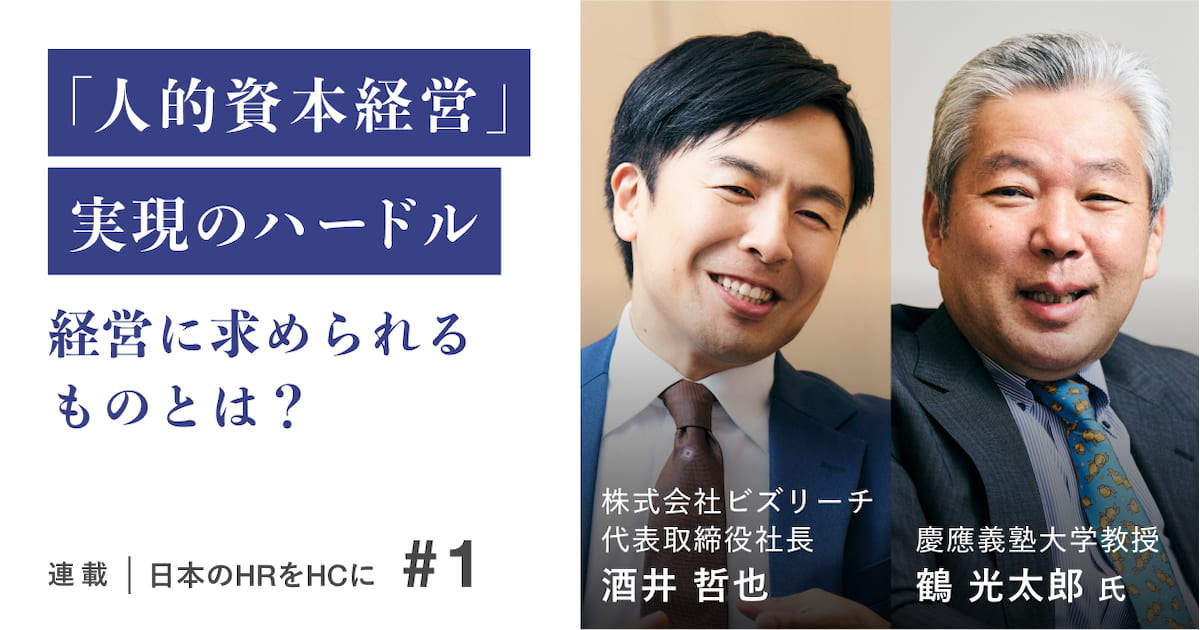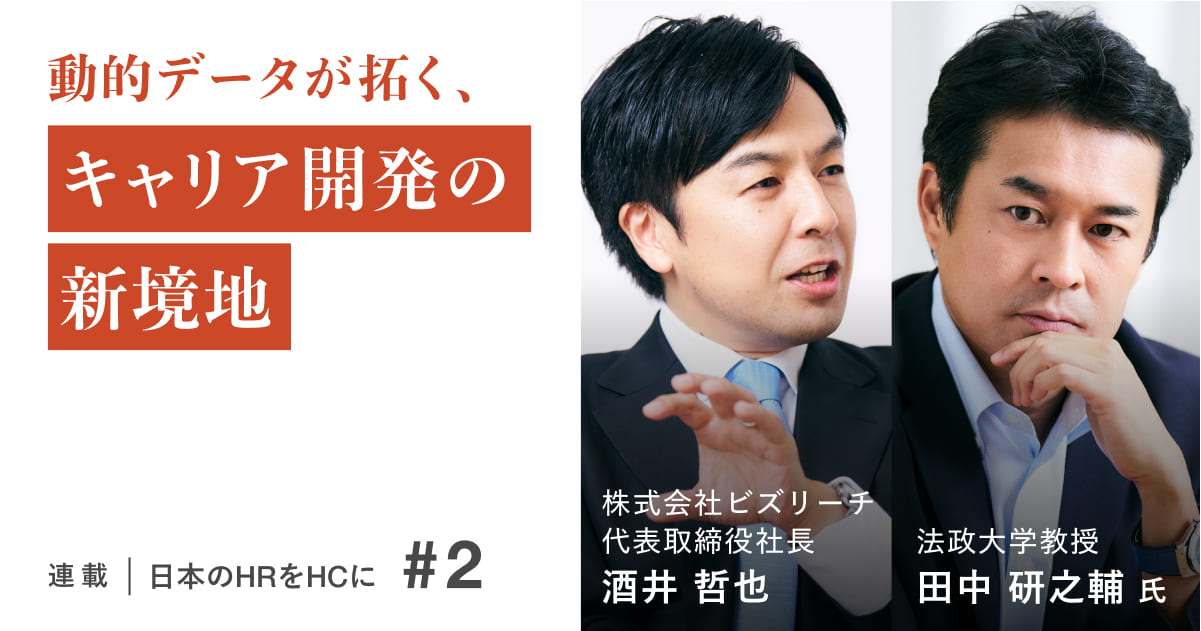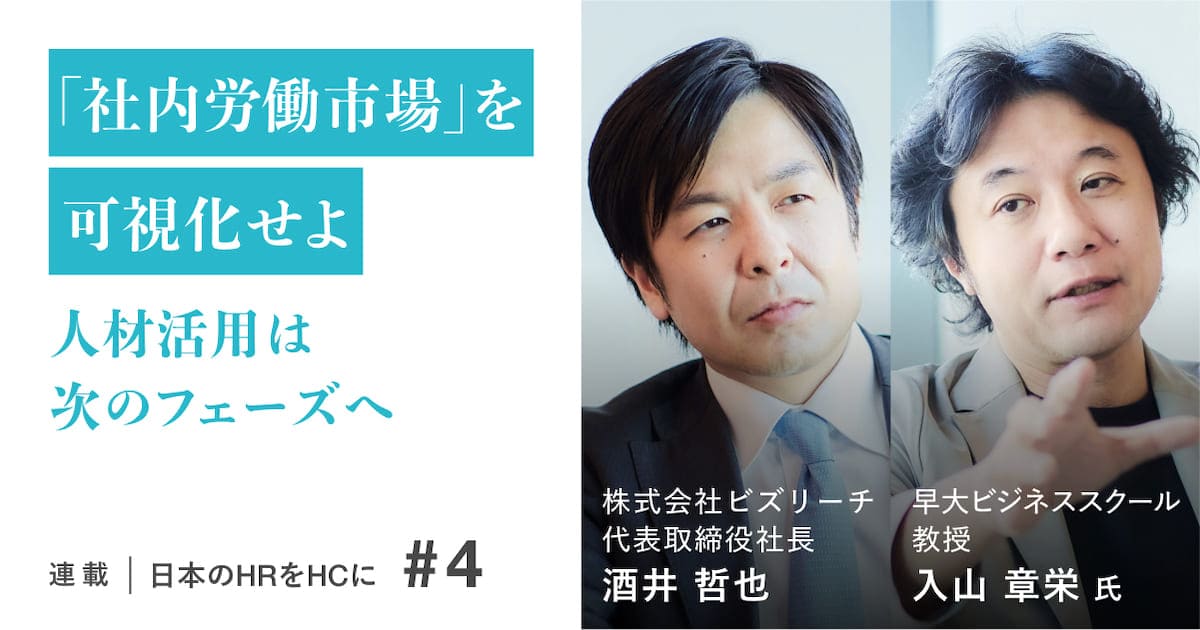連載 日本のHRをHCに
「人も組織も、常に自ら変わる準備を」
東京大学教授 柳川 範之氏
×
株式会社ビズリーチ代表取締役社長 酒井 哲也
「日本型」といわれた働き方の大転換期にある日本の産業社会。東京大学大学院の柳川範之教授は、「社会や企業の構造を変える必要がある」と話します。変化の激しい時代に適応できる人や組織とは。当社社長の酒井哲也が伺いました。
足りないのは「変わるための方法論」
酒井
ビズリーチは親会社のVisionalとともに、「100年続くことよりも、100回変わる会社」を掲げています。そのために「変わり続けるために、学び続ける」というバリューを大事にしているのですが、柳川先生も近著の中で「生き残るためには変わらないといけない」ということをおっしゃられています。
柳川
そうですね。端的に言うと働く環境の変化がとても大きく、それに対応しなければ個人も企業も生き残っていけないということです。
一番分かりやすいのは技術革新で、AI(人工知能)などが急速に仕事のやり方を変えています。また年功序列や終身雇用、専業主婦世帯などいわゆる「昭和モデル」を前提とした働き方がうまく適応できなくなっています。これらは一時的な変化ではありません。法律や制度、企業の中の仕組みなど構造を変えないと、世の中がうまく回らない時代になったと思います。

- プロフィール
- 柳川 範之(やながわ のりゆき):東京大学大学院経済学研究科教授。経済産業省の「未来人材会議」座長。中学卒業後、父親の海外勤務の都合でブラジルへ行き、現地では高校に行かず独学。大学入学資格検定(大検)を受け慶応義塾大学に入学した経歴から、「学び方」に関する著書も多数。
酒井
ビジネスモデルの寿命も短くなっています。私が学生のころ、富士フイルムという会社はレンズ付きフィルム「写ルンです」の会社というイメージでした。それがデジタル化の波でデジカメが主要商品になり、今や医薬品や化粧品を主力事業としています。こうした劇的な変化が、あらゆる業種で必要になるということでしょうか。
柳川
「変わる必要性」はかなり世の中に浸透してきている気がします。しかし「ではどうするか」という方法論が確立していません。そのために、まだ行動を変えられていない人や組織が多数派、という状況ではないでしょうか。
バブル以前、高度成長期は米国というベンチマークが明確で、米国のあの企業のような会社を、あのような製品を作ろう、それでよかったわけです。しかし今や日本も先進国化して、分かりやすい目標がなくなりました。10年後の必勝戦略がなく、個人も企業も手探り状態です。
普段から、1つの手法にこだわらない姿勢を
酒井
自戒を込めてですが、いわゆる過去の成功体験のバイアスはとても大きくて、それまでの行動を変えるというのは非常に難しいことです。
行動を変えられない典型的なパターンは2つあると思っており、1つは変化の「1歩目」が出ないということ。1歩目さえ出てしまえば2歩目は自然に出る部分もあると思いますが、どっちに向かっていいか分からないために足が出ないケース。
もう1つのケースは、「変えよう」という意識はあるのに、それまでのやり方が染みついていて無意識に同じやり方をしてしまうということもありますよね。

- プロフィール
- 酒井 哲也(さかい てつや):2003年、慶應義塾大学商学部卒業後、日本スポーツビジョンに入社。その後、リクルートキャリアで営業、事業開発を経て、中途採用領域の営業部門長などを務める。2015年11月、ビズリーチに入社し、ビズリーチ事業本部長、リクルーティングプラットフォーム統括本部長、取締役副社長などを歴任。2022年7月、ビズリーチ代表取締役社長に就任。2022年10月、ビジョナル取締役を兼任。
柳川
元陸上選手の為末大さんとの共著「Unlearn(アンラーン)」でまさにそのあたりのことを取り上げています。
アスリートの説得力はさすがだなと思うのですが、彼らはまさに「無意識に体が動く」ところまでトレーニングをするわけですよね。しかしそのやり方では勝てなくなったり記録が出なくなったりします。そのたびに、無意識にできるようになった動きを変え、新しいやり方を体に刻むように練習する必要に迫られます。
せっかく身につけたものを変えるのは苦しいものですが、それをやらなければ勝てないので、変えないという選択肢はほぼありません。必要なのは「このやり方もいつか変える必要がある」という認識をあらかじめ持っておくことというんですね。1つのことに拘泥しない意識を普段から持っておくということだと思います。
酒井
個人的にも共感するお話です。完璧な計画を作ろうとして、それにこだわりすぎると、何かあったときにポキッと折れてしまう。建造物の免震構造のようなイメージですが、ある程度は揺れることを前提にした「あそび」の部分を持っておき、何かあれば別のことを考えられるようにしておくのは、個人としても経営者としても非常に大事な意識だと感じます。
そうした意識を持つために、何かできることというのはあるのでしょうか。
柳川
1つは、普段からイレギュラーを受容したり、自分で決めたりする体験をしておくことかなと思います。よく「清水の舞台から飛び降りるつもりで」と言いますが、いきなりそんな高いところから飛べと言われたって、そんな勇気は出ないのが普通です。
でも普段から小さなステップでもいいから、決断し飛び出す体験をしていれば、いざというときにジャンプできる可能性が高まります。なんでもいいんですよ。例えばいつも同じランチを食べているなら別のものにするとか。思考実験的に頭の中だけででも、「こっちが傾いたら、こっちをやろう」とか、そういうことを考えるクセをつけることが大事だと思います。
もう1つは、決定を会社や他人任せにしないことですね。自分が主体的に考えられないと環境変化に対応できません。先ほどのランチの例で言えば、普段から誰かが言ったものに「私も同じ」って注文する人が、いざ大事なときに「自分はこうする」ってはっきり言えますかね。ランチはただの例ですけれども、なにごとも付和雷同せず、自分で考えて決めることに慣れておくのは大事だと思います。
絶対に外さない「軸」と「監督の目線」を持て
酒井
こうした話のときに思うのは、変化が大事だということばかり強調してしまうと「なんでもあり」という誤解が生まれかねないということです。先ほどの建造物のたとえで言うと、耐震構造でも免震構造でもいいけれども、目標は「地震が起きても立っている」ということなわけですよね。経営としては、そういう絶対に外さない「軸」を明らかにしておくことも重要だなと思うんです。
個人の場合も同じです。転職サービスの社長としては夢のないことを言うようですが、私は「すべての希望を100%満たす転職なんてない」と思っています。不動産の物件探しと考えれば分かりやすいと思いますが、こちらを立てればあちらが立たず、というなかで決断を迫られることがほとんどです。そのときに必要になるのが「これだけは絶対かなえたい」という軸です。
企業も個人も、そうした軸となる考えは多種多様です。互いにそれを把握するのは至難の業なので、当社が提供しているようなマッチング機能が必要になるのだと思います。
柳川
そうですね。企業も働き手も多様で複雑なニーズを持っています。皆さんのようなマッチング、人材サービスが埋めてくれる部分はとても大きいと思います。
一方で指摘しておきたいのは、現状においては情報の非対称性がかなりあります。要するにいくら丁寧にマッチングや選考をしても「働いてみないと、雇用してみないと分からない」という部分が大きいんですよね。互いに手に入る情報がもっと多く、精度も高くなれば別ですが、現状においてマッチングだけでベストなチーム編成ができるかといえばなかなか難しいと言わざるを得ません。
できることは、酒井さんがおっしゃるようにそれぞれが選球眼を養うことです。個人にお勧めしたいのは、チームの監督になったつもりで企業が「どういう人材を求めているか」を普段から考えておくことです。
事前に分からないことは確かに多いのですが、労働市場では誰も「あなたのために」最適なチーム編成をしてくれるわけではありません。選手目線で「自分が活躍できる場所はどこか」と考えても、どこにもハマらなかったり、多くのライバルがいたりというケースがあります。
そうではなく、監督、つまり管理職や経営者の目線で「どんな人を求めているか」を考え、自身をそこに近づけていくのです。監督は常に「こんな人材が欲しい」と思っていますが、やらせてみないとピッタリ合うか分かりません。そうしたときに「欲しいのはこういう人材ですよね」と言える選手がいたらどうでしょう。場合によっては、スキルはピッタリではないかもしれませんが、「ここが求められている」という問題意識がそろっているのは確認できます。アドバンテージになりますよね。

人事領域でのデータ活用は不可避
酒井
とても重要なご指摘です。当社がやらなくてはいけないのは、そうしたことを考えるための材料提供ですね。例えば、「この企業のこのポジションで活躍してきた人はこういう傾向がある」とか、「自分と似た経歴の人が、その後こんなキャリアを築いた」とか、そういったことが定量的に分かれば、「監督の目」を持ちやすくなると考えています。
当社はこれまで、ビズリーチという転職のサービスで外部労働市場をメインの領域としてきました。しかしこれからは、企業内のデータもそれに連携させることで、社内外からの人材登用・配置をシームレスにアシストしていきたいと考えています。
転職はキャリアの瞬間的な出来事にすぎません。本質的に重要なのは人の活躍を最大化することで、そのためには所属企業での活躍具合も知る必要があります。それを把握できれば、転職のマッチングもさらに精度を高めていけます。
柳川
これからの人事領域において、データの活用はなくてはならない要素です。スポーツの世界でどんどんデータ化が進んでいるのは、それが「勝利」という成果に有効だからです。
競技はルールが明確でデータ化しやすいという面があるため、そのままビジネスシーンに応用できるかといえば難しい部分はあります。特に人事領域は、定量的に測りにくい部分があることも確かです。しかし、それを言い訳にしては生産性の向上は望めません。
酒井
人を「資本」としてとらえる人的資本経営を根付かせるためには、その資本をどれだけ価値創造につなげられるかという点で、定量的なアプローチが必要になりますよね。
柳川
おっしゃる通りです。ただ「人的資本」がカネやモノと違うのは、その価値は会社に蓄積されるのではなく、個人に帰属するところです。特殊な知財などではない限り、価値は個人に蓄積されるのです。だからこそ「教育投資をしても転職で外部に流出するじゃないか」という考えが出てきてしまいます。
人的資本の考え方というのは、人の資本を最大限生かし、その成長機会も提供する会社だからこそ、価値を創造する人材が集まり、競争力が高まるというものです。定量的な数値計測は重要ですが、その運用の仕方には注意が必要と感じています。
新たな仕組みに戸惑う人には支援を
酒井
長く大学で教鞭(きょうべん)をとられていますが、以前の学生と今の学生のキャリア観で変わってきていると感じることはありますか。
柳川
全く変わってきたと思いますよ。少なくとも私の周囲の学生は「自分がどれだけ成長できるか、自己実現できるか」というので就職先を選ぶ。会社ブランドを重視して「この会社に一生いよう」という感覚の学生はほぼゼロですね。90年代は、基本的にはみんな一生活躍できるところを目指していましたけどね。
酒井
教育プログラムが変わってきたということもあるのでしょうか。
柳川
そうですね。例えば授業で「起業プログラム」というのを10年くらいやっているんですが、以前は実際には登記をしない「バーチャル起業」でした。それはいくら授業の一環とはいえ、会社を作ってつぶすということが、就職で不利になるのではないかといったような抵抗感があったからです。
今はそれが、デメリットどころかメリットという評価になった気がします。そういう意味では学生もですが、採用する企業の感覚も変わってきたのでしょうね。
酒井
「ビズリーチ・キャンパス」といって、新卒学生向けのサービスも手掛けているのですが、これは簡単に言うと「自分と同じ大学出身の先輩にOB/OG訪問する」というものです。今のところ、学生にとってそれが一番自分の未来を想像しやすいものだと思っています。ただ、先ほどお話ししたキャリアのデータが蓄積できれば、そうした未来像ももっと定量的に示せるようになっていくと思います。

柳川
雇用が徐々に流動化して、大学生もみんな手探りです。どの会社でどんなスキルを身につけたら、どうなっていくのか。それをみんな知りたいと思っているので、非常に有用なお話だと思います。
逆に企業として難しくなってきているのは、世代によってキャリア意識が大きく違うということですよね。終身雇用を前提にしていたシニアと、転職を辞さず、転勤などを受け入れられない若年層。考え方が全然違う人材が混在しているので、一律の労働契約や人事制度で対応しきれなくなっています。ここが非常に難しいところです。
結論としては新しいやり方に適応していくことになるはずですが、それまでずっとやってきた仕組みをいきなりやめろと言っても難しい方も多い。適応のためにはガイドが必要でサポートする存在が必要です。
昨今リスキリングということが盛んに言われますが、デジタルスキルを身につけるといったことに目が行っているようにも思います。まず必要になるのは、主体的にキャリアを考えるという姿勢のインストールだと思いますね。
酒井
本日はありがとうございました。