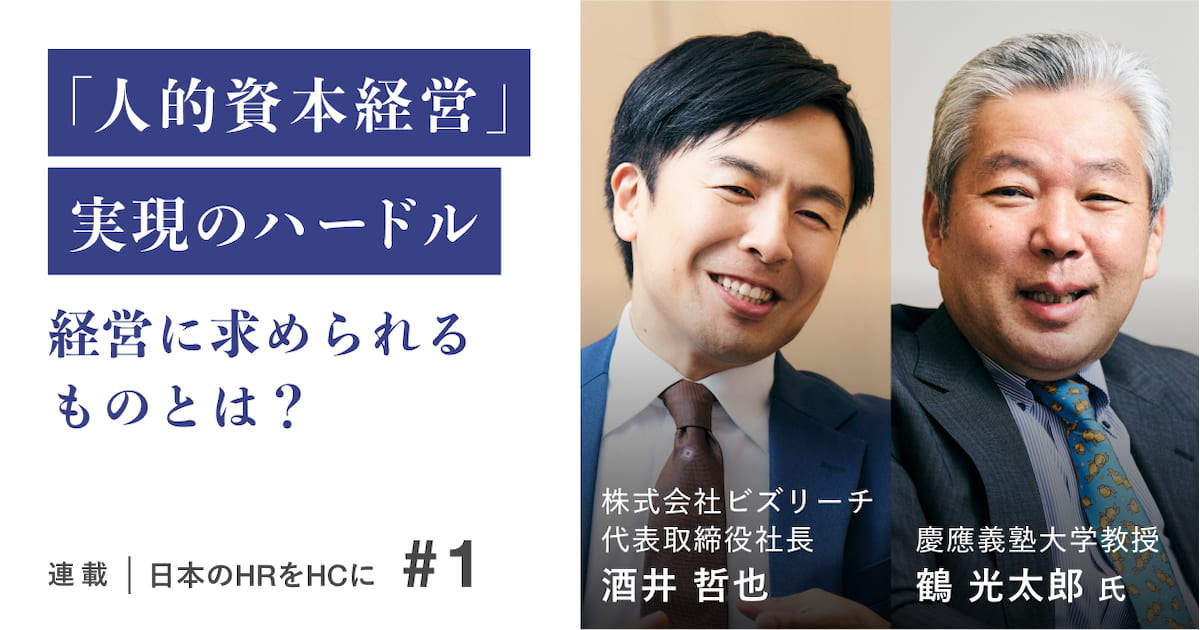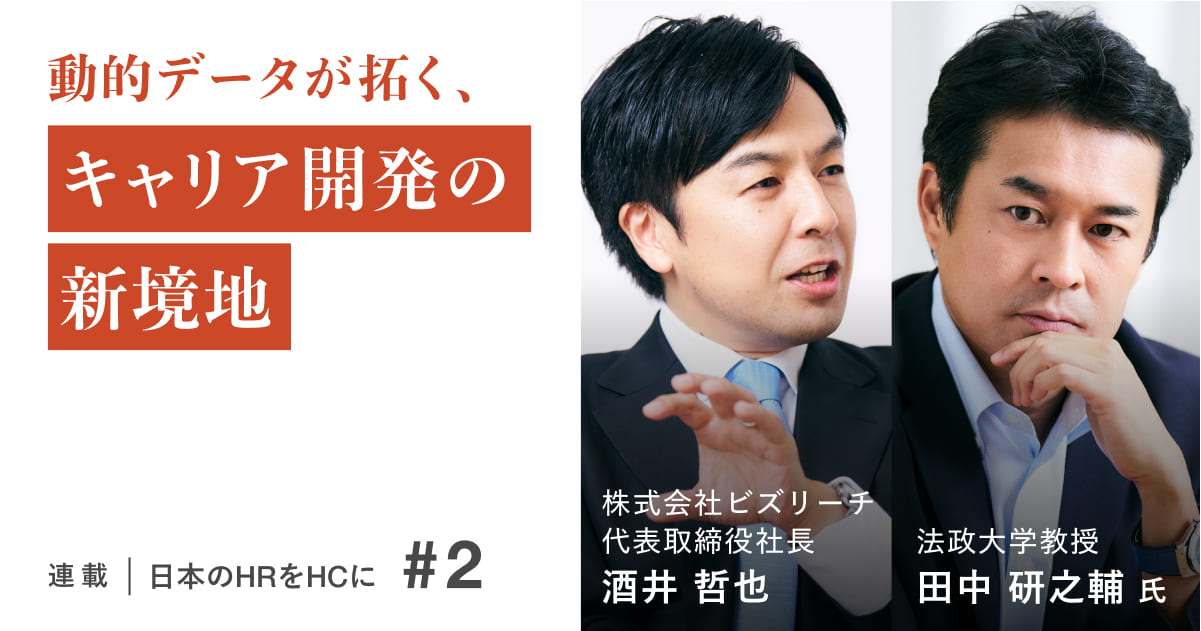連載 日本のHRをHCに
イノベーションのカギは人事とCHRO
ぼやけてきた「社内」と「社外」の労働市場の境界線
早稲田大学ビジネススクール教授 入山 章栄氏
×
株式会社ビズリーチ代表取締役社長 酒井 哲也
企業が競争を勝ち抜くためには、これまで以上にイノベーションが重要だと言われるようになりました。しかし、日本企業では十分にイノベーションが起きていないとも言われます。イノベーションを生むために、人事ができることはあるのか。企業の競争戦略を専門とする早稲田大学ビジネススクールの入山章栄教授に、当社社長の酒井哲也が伺いました。
日本企業で「イノベーションが起きづらい」わけ
酒井
入山先生は経営戦略やイノベーション理論をご専門とされています。日本企業が今後、競争力を高めていくために必要なこととは何でしょう。
入山
日本の最大の課題は、人事だと言っても過言ではないと思います。会社というのは人と組織でできています。本来、人は会社の根幹であり、企業ごとに戦略的に動かしていくべきものです。
20世紀を代表する経済学者で「イノベーション理論」を提唱したシュンペーターの主張によれば、イノベーションは、離れたところに存在する知見と知見の掛け合わせによって生まれます。そしてその知見を持っているのは「人」にほかなりません。知見の掛け合わせとは、要は人同士の掛け合わせなんです。
しかし日本の産業社会では、過去のいい時代にいわば「受け身の人事」が定着してしまいました。メンバーシップ型の雇用・人事制度によって組織内が同質化し、イノベーションが起きにくくなってしまったのです。最近ようやく人材の流動化が始まってきましたが、まだまだ十分ではありません。
日本企業は全体としてPER(株価収益率)が低いですよね。これは要するに「利益は上げられるけど、市場には評価されていない」ということです。市場評価には未来の成長期待が含まれていますから、換言すればあまりイノベーションを起こせるとは思われていないと言えるでしょう。

- プロフィール
- 入山 章栄(いりやま あきえ):早稲田大学大学院経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール 教授。慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所で、主に自動車メーカー・国内外政府機関への調査・コンサルティング業務に従事したあと、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.(博士号)を取得。「Strategic Management Journal」など国際的な主要経営学術誌に論文を多数発表。
酒井
流動性が高まっているのは感じますか。
入山
それはとても感じます。私のビジネススクールの学生も、夜のプログラムの入学志望者の倍率は今5倍くらいなんです。1学年300人なので、年間にざっと1,500人が受けていることになります。
そうした方が考えているのは、次のステップとしての転職です。もちろん社内で活躍するためにという理由もあると思いますが、どちらかと言えば社外にも活躍の場を広げるためにビジネススクールに来ているという印象です。
酒井
自らビジネススクールに行く方は、まだ動ける方なのだと思います。でも年を重ねるほど「スキルを身につけるとどうなるのか」が見えないと、なかなかそうやって踏み出していけないという声も聞こえてきます。
入山
おっしゃる通りです。私自身、大学以外にも多くのお仕事をさせていただくようになったので、「外の仕事をどれくらい受けると、いくらくらいの収入になるか」といった感覚があります。
しかし、1社にずっと勤めている方はそういった感覚がない方が多いですよね。私はよく漫画やアニメ作品に例えるのですが、ドラゴンボールに「スカウター」ってあるじゃないですか。敵の強さを数値化して測ってくれる機械ですが、ああいった「社内だけじゃなくて普遍的に通用する基準」があれば、人はもっと決断しやすくなります。
そういう意味でも、わたしはビジネススクールの学生みんなに「ビズリーチに登録した方がいい」って言ってます。外部からの目を意識するきっかけになりますからね。
「社内労働市場」を可視化する
酒井
当社はこれまで外部の労働市場における価値の可視化をやってきました。実は今、これを社内でもできるようにしたいと思っているんです。
もちろん、人事の情報って社内にあるのですが、人を的確に探せるようになっているかと言えば、必ずしもそうではありません。
例えばAさんの後任を探すときに、「Aさんみたいな人はいないか」と思うことは多いでしょう。しかし「どういう特徴があればAさんみたいと言えるのか」は難しい問題です。そうするとマッチングができません。この課題を、当社が「ビズリーチ」で培った技術で乗り越えようという考え方です。

- プロフィール
- 酒井 哲也(さかい てつや):2003年、慶應義塾大学商学部卒業後、日本スポーツビジョンに入社。その後、リクルートキャリアで営業、事業開発を経て、中途採用領域の営業部門長などを務める。2015年11月、ビズリーチに入社し、ビズリーチ事業本部長、リクルーティングプラットフォーム統括本部長、取締役副社長などを歴任。2022年7月、ビズリーチ代表取締役社長に就任。2022年10月、ビジョナル取締役を兼任。
入山
まさに次の課題に取り組まれていると思います。おっしゃるように、可視化されていない人事の情報は社内にたくさんあるように思います。意外と一番頼りになるのは人事評価そのものではなく、社内の「うわさベース」の話だったりもします。
酒井
私たちビズリーチは、社外での人材流動化を進めてきましたが、これを企業の内側でもできるようにすれば、働く方の選択肢は大きく広がると思っています。そして企業からすれば人材流出をとめることにつながります。
入山
よく考えると、人事領域で社内と社外のデータを両方持っているビズリーチは、極めて特異な存在ですね。
酒井
はい、私たちとしてもそこは強く訴えていきたい部分です。大手企業だとスキルや経験を記載するときに、社内でしか分からない言葉で記録されていることがあります。しかしそれを、社外の労働市場とそろえることで、個人は「自分の市場価値」を知ることができます。
働く個人が外部の可能性を探るようになると、会社としても、労働市場に合わせて対応していかないと「井の中の蛙(かわず)」になってしまいます。競合企業が待遇を改善しているのに、自社の基準だけで優秀な人材を処遇しようとしても、待遇が十分ではなくなる可能性があります。
入山
社内異動のことを考えると、いろんな部署から引っ張りだこになる優秀な人材って、所属部署に抱え込まれてしまう傾向があると思います。でももし、客観的指標で「この仕事に最も適性があるのはこの人です」ということが分かったら、社内での流動化も進みそうです。
人事の専門家以外もCHROに
酒井
私はよく野球に例えてしまうのですが、例えばメジャーリーグのセイバーメトリクスっていうデータ分析を使うと、さまざまな指標をもとにある選手に近しい選手をマッピングして表示してくれます。「似ている度」が、チーム内外で可視化されるわけです。
それと同様に社内外からシームレスに、求める人材を探せるようにするのが目指している世界です。
入山
これだけの人手不足なので、その必要性は多くの企業が感じているのではないでしょうか。われわれのような研究者と一緒にビズリーチが先行して、これだという指標を作って世の中に浸透させれば、ものすごい変化が生まれると思います。
日本で働く方は長い間「社内」と「社外」をきっぱり分けていました。でも今は、だんだんとその境界線がぼやけてきていると感じます。
私はロート製薬の社外取締役をやっていますが、ロート製薬は日本のほかの大手企業に先駆けて副業を解禁しました。最初は社員にほかの職場で副業していいよ、というものでしたが、今はロート製薬で副業をしたいという人も受け入れています。
企業にとっても個人にとっても、社内外の情報を把握するのはもっと必要になってくるでしょうね。
酒井
イノベーションを起こしていくために、企業の人事部門に求められることは何でしょう。
入山
まずは部門というよりも、CHRO(最高人事責任者)がカギだと思います。日本で「人事課題」っていうと、人事制度や働き方のような「労務」に関することがイメージされがちです。そちらも重要ではありますが、もっと大事なのは経営戦略を実現するための人事戦略の推進で、これは経営戦略そのものであり、それこそがCHROの仕事だと思います。
そう考えると、CHROには事業に対する理解も求められます。これまでのように「人事一筋の専門家」ではなく、まったく違う経験をしてきた方がCHROになるなど、さまざまな方がCHROを担っていくようになるかもしれません。

酒井
パナソニック ホールディングスが、メルカリでCHROをされていた木下達夫氏をCHROに招くなど、確かにそうした動きは活発化しています。
入山
木下さんのお仕事には、私も注目しています。ほかにも昭和電工でCHROをされて、レゾナックでもCHROに就いた今井のりさんとお話しする機会があったのですが、彼女も決して人事の経歴が長いわけではありません。
酒井
当社でもそうした意識があり、もともとビズリーチの営業部門のトップだった人材をこのほど人事のトップに据えました。もちろん、人事を長く経験されてきた方がトップを担うことを否定するものではありません。しかし、事業と人事をより近づけていく必要があるというのは、ご指摘の通りではないかと思います。
「失敗できる人事」に
入山
もう一つ、今の人事に求められていることは「失敗すること」だと思います。イノベーションを起こしていくには、失敗してそれを乗り越えるという体験が必要です。ですが私の印象では、人事は法務部門と同じくらい保守的な組織であることが多い。
終身雇用のもとでは、企業の人事は「社員の人生を預かっている。だから失敗は許されない」という責任感を抱きがちです。でもこれは、私に言わせれば「謎の責任感」です。プライベートでどんなことが起きるのかも分からないのに、企業が個人の人生に責任なんて持てません。
よほど取り返しのつかないことを別にすれば、戦略的な採用や異動、教育、人事制度改革など、もっと人事も挑戦をしていいはずです。施策に失敗はつきものですし、社内にハレーションを生むこともあるでしょう。しかし、社内からのさまざまな声を調整し、経営と合意形成できるのが優秀なCHROなのだと思います。
酒井
誤解を恐れずに言うと、人事の施策で「100%全員が満足する」ということはないのだと思います。だからこそ企業は「自分たちはこういう会社で、こういう人に手厚く報いる」といった考え方を示す必要があるように感じます。
入山
はい。いい会社って、だいたい「宗教的要素」があるんですよ。昨年、ジャーナリストの池上彰さんと『宗教を学べば経営がわかる』(文春新書)という書籍を出させていただきました。経営戦略などにはあまり違いがなくても、みんなで同じ方向を向いて、どれだけ頑張れるかというところで、競争力に差が生まれます。
こう言うと「教祖」のような方の存在の大事さを訴えるように聞こえるかもしれませんが、教祖に頼るのがいいわけではありません。会社が大きくなったり、長い年月が過ぎて創業者がいなくなったりしても、従業員に信じてもらい続けるためには、仕組みも必要です。
「パーパス」の重要性も語られるようになりましたが、バイブルのような形で言語化したり、普段から目に触れる機会を作ったりといったことが重要です。30~40年先の未来に向かって、意志を決めてバトンをつないでいくのが経営なので。
個人が「キャリアを自分で決めた」と思えるために
入山
ところで、今後のビズリーチはどうなっていくんですか。人事コンサルティングなどはやらないのでしょうか。
酒井
実際、そうした引き合いは多く、既存のお客さまでも採用のサポートをする過程で、コンサルティング的な役割を果たすこともあります。これまではプロダクトをご契約いただき、利用してもらうことで成長してきましたが、今後はコンサルティング機能も拡大していくつもりです。
あとはやはり、先ほども触れましたが「社内の人材活用」ですね。
入山
御社には本当に期待しています。企業はもっと「こう働くべきだよね」っていう方向感を示す必要があると思っています。ところが、多くの企業がそれを言語化できていません。
日本の課題の一つに、東京に仕事と人材が集中していることがありますが、承継者が決まっていない地方の有力中小企業とか、日本全体でダイレクトリクルーティングができると、課題の解消につながる部分もあると思います。
酒井
まとめてしまえば、流動化の促進だと思うんです。仮にある会社や部署で「自分は必要とされなくなった」と感じるようなことがあったとしても、他の場所では大いに必要とされるということは絶対にあります。

入山
少し前に「半沢直樹」というドラマがヒットしましたよね。お話としては面白いですが、現代の企業社会を前提にしちゃうと違和感があるのは、「そんなに嫌な会社なら、倍返しなんてしてないで辞めればいいのに」と思ってしまうところです。
あのドラマは「キャリアに自己決定権がない」「個人にそれを持たせない」という、メンバーシップ型の雇用慣習を前提としています。でも今は、日本でも個人が自己選択するようになってきています。その変化に対応するための仕組みが、個人からも企業からも求められているのでしょうね。
酒井
「人事も失敗していい」というお話がありましたが、キャリアにおいて大事なのは、自分で納得して選択したかという感覚なのだと思っています。未来は分からないし、失敗もあるかもしれない。でも自分で決めたことだったら、たいていのことは「自分で決めたんだから頑張ろう」となると思うんです。
入山
納得です。私自身、30歳で三菱総合研究所を辞めて、アメリカで博士号をとったときはかなり大変な思いをしましたが、自分で決めたからには、と思っていました。
酒井
まずは自分にどんな選択肢や可能性があるのか、それを社内、社外問わず、分かるようにしていくのが当社の役割だと思っています。本日はありがとうございました。